(戻る)
このアーカイブスは、先端情報技術研究所(AITEC)の役割のうち、下記の1.に関する情報を整理したものである。
- 国が行う研究開発の仕組み、法制度のあり方についての調査と改革提言
(平成7年度:FY1995-平成14年度:FY2002)
- 第五世代コンピュータ技術の普及活動(平成7年度:FY1995-平成10年度:FY1998)
利用条件
先端情報技術研究所の調査の動機と目的
- わが国のIT研究開発、特にソフトウェアR&D投資 ==> 投資効率が悪い、IT産業へのインパクトが少ないのはなぜか
わが国の国が行う情報技術(IT)の研究開発、特に、ソフトウェアの研究開発については、開発投資に対し、その成果が十分でないように見える。
わが国で開発され世界市場で大きなシェアを獲得したソフトウェアがない。また、わが国のソフトウェア産業の競争力は米欧にくらべ弱く、最近では、インドや中国などのIT新興国の追い上げを受けている。
-
- わが国のIT研究開発の投資や商品化の仕組みや法制度に問題があるのではないか ==> 米欧諸国などとの比較
これに対して米国は、技術貿易に時代に入り、Windowsなどの基本ソフトウェアの分野で世界を凌駕するだけでなく、特許や
著作権などの、いわゆる知財権(IPR)の分野でも圧倒的な強さを発揮している。
-
- ここでは、このような米国の強さを生み出す元となっている、連邦政府が支援する研究開発の仕組み、法制度を調査し、わが国のナショプロとの比較を行い、わが国のナショプロの仕組み、
法制度の問題点を指摘し、その改革提言を行うことを目的としている。
-
- 米国の研究開発計画(イニシアチブ)としては、HPCCとして始まり、 クリントン政権の副大統領であったアル・ゴアの提唱したNational
Information High-Way (NII)による拡張などを取り込み、現在はNetworking and Information Technology Research and Develoment (NITIRD)計画に発展している研究開発の流れにそった仕組み、法制度を主要な対象としている。
AITECが作成した報告書や関連資料の総目次
1. 各年度の総合報告書: わが国が行う情報技術研究開発のあり方に関する調査研究
- 平成8年度(その1) --------> 平成14年度(その7)
- 各年度の中核的調査テーマ、調査概要を説明して、年度を通しての調査の流れを示す。また、各年度において、
実施した関連調査テーマ、および、その報告書の一覧を添付して総目次とする。
- 1.1 平成7年度
- 中核的調査テーマ
米国政府機関を対象とした、先端情報技術への研究投資の現状について
- 調査の概要
米国政府機関としては、NSF、DOE、NASA、DARPAなどを中心に、下記のような点について調査した。
a) どのような政府機関から、どのような研究組織の、どのようなテーマに、投資されているのか
b) 将来花開くであろう情報関連基礎テーマで、重点投資が行われている分野はどこか
c) 研究実施機関をサポートするインフラや設備投資に、どんな措置が取られているか
d) 基礎研究を実際のビジネスに育て上げるための方策は、どうなっているのか
- 関連調査テーマ
・ 米国の先端情報技術に関する調査研究 HTML
・ 米国政府による情報技術研究開発運営の現状と技術開発動向 HTML
- 1.2 平成8年度(その1) (全文) HTML
- 中核的調査テーマ
米国政府の情報技術政策と研究開発の仕組み、およびわが国の情報技術研究開発実施上の問題点
- 調査の概要
米国の情報技術政策は、IT技術およびそれを構成するソフトウェア技術開発の目標を、明確に定めている。それにより、国のインフラとなるような大規模なソフトウェアから、商品化を目指すものまで、社会的ニーズ、国家的ニーズなどを考慮して、研究開発の位置付けや目標が定められている。また、研究開発テーマやその実施に関しても、目的に応じた仕組みが準備され、合理的な政策と研究開発目標が設定されている。
一方、わが国の研究開発は、各省庁の役割に応じてテーマや予算が決められ実施されるが、ITやソフトウェアのような広範囲にわたる研究テーマに関しては、テーマや実施体制を、国全体として考える組織、仕組みが米国等に比べて未整備であり、十分機能していない。
本調査では、米国の組織、仕組みについて調査し、わが国の抱える問題点について指摘する。
- 関連調査テーマ
・ ペタフロップスマシン技術に関する調査研究 HTML
・ ネットワーク及びAI関連新技術に関する調査研究 HTML
・ 米国における政府系研究予算の戦略的決定・執行体制 HTML
・ 米国情報産業における研究成果の製品化・市場創造プロセス HTML
・ 日本における情報技術関連研究開発プロジェクト HTML
・ 情報関連産業への国の投資による経済効果予測 HTML
・ 平成7年度-8年度 技術調査部の活動報告 HTML
・ 平成8年度調査活動報告概要 HTML
- 1.3 平成9年度(その2) (全文) HTML
- 中核的調査テーマ
米国における研究開発成果の技術移転と起業および中小企業の育成支援
- 調査の概要
研究開発によってアイデアから商品が生まれ、起業が行われる。米国では、この研究開発の上流から商品化を行う下流まで、シームレスな支援の仕組みが準備されている。さらに、起業をした後についても、その企業が発展しているような育成を支援する仕組みがある。本調査では、国による中小企業からの優先的調達、国立研究所で開発された成果の民間への技術移転、そして、国の支援ではないが、企業の拡大によく用いられるM&AのIT産業における典型例について調査を行っている。
- 関連調査テーマ
・ ペタフロップスマシン技術に関する調査研究Ⅱ HTML
・ 人間主体の知的情報技術に関する調査研究 HTML
・ 米国における情報技術企業のM&A戦略 HTML
・ ソフトウェア産業振興のための国の役割(アンケート調査) HTML
・ 米国政府の政府調達にみる中小企業支援制度 HTML
・ 米国国立研究所の運営形態と技術移転 HTML
・ 欧州の主要情報技術プロジェクト HTML
- 1.4 平成10年度(その3) (全文) HTML (概要)
HTML pdf

- 中核的調査テーマ
国が支援する情報技術開発施策における産業界が抱える問題点
- 調査の概要
国の支援する情報技術開発施策は、その大局においては、わが国の産業の国際競争力を高めることを目指すものがほとんどである。したがって、研究開発の目標、実施体制、実用化に係わる条件なども、産業界が国際的競争環境において、有利になるように設定されるべきである。しかしながら、研究開発の原資となる国の予算の大枠に起因する制約などにより、その研究開発予算の合理的使用が大きく制約を受けるなどの場合がある。その一例は、景気浮揚の補正予算などを利用した場合である。その他、人件費の使用についても、ソフトウェアの時代に合わなくなった箱物作りの時代の法・制度が改定されず、生き残り、わが国の情報技術開発における資金の効率的利用を妨げている。この調査では、メーカよりのヒヤリングや、米欧の仕組みとの比較を行い、わが国の産業界の抱える問題を調査している。
- 関連調査テーマ
・ ペタフロップスマシン技術に関する調査研究Ⅲ HTML
・ 人間主体の知的情報技術に関する調査研究Ⅱ HTML
・ わが国における政府支援プロジェクトの知的財産権の扱い HTML ポイント(HTML)
・ 米国の政府支援研究開発プロジェクトにおける知的財産権の取り扱いの変遷の歴史とその背景 HTML ポイント(HTML)
・ 米欧の研究開発プロジェクトにおける知的財産権の取り扱い HTML ポイント(HTML)
・ 米国の情報産業技術振興政策の事例研究 HTML ポイント(HTML)
・ 先進諸国における情報化ビジョンに関する動向 HTML ポイント(HTML)
・ 平成10年度調査事業報告および平成11年度以降 の調査事業方針(案) HTML pdf
- 1.5 平成11年度(その4) (全文)
HTML (要旨)
HTML pdf

- 中核的調査テーマ
国の情報技術開発におけるわが国の大学・国研の問題点、および制約の多い会計制度
- 調査の概要
情報技術、特にソフトウェアの新分野・新商品の開発には、オリジナルなアイデアから基礎研究段階を経てその研究を発展・拡張し、下流の商品化研究に至る各段階が必要である。米国では、大学・国研の研究者がこの役割を担っている。特に、大学においては、プロジェクト予算での研究者の雇用が可能であることから、ポスドクの学生を始め、多くの研究専門のスタッフが活躍し、その成果がメーカへ技術移転されている。また、研究者自身がベンチャー企業を起こし、新しい市場を創造し、情報産業発展に大きな役割を果たしている。
一方、わが国の大学・国研では、そのような研究専門のスタッフはほとんどおらず、大学において、商品となるようなソフトウェアやシステムの開発は困難である。そのため、論文主体の研究が行われ、メーカや市場の求める技術を生み出してはいない。この違いが日米のソフトウェア産業の実力の格差の大きな要因の一つである。この原因の一つに、わが国の制約の多い会計制度と、国の研究管理の仕組みがある。本調査は、日米の仕組み、法・制度を比較し、その原因を究明する。
- 関連調査テーマ
・ ハイエンドコンピューティング技術に関する調査研究Ⅰ - ペタフロップスを中心とする - HTML pdf
・ 人間主体の知的情報技術に関する調査研究Ⅲ HTML pdf
・ 米国の政府支援研究開発における効率重視のマネジメント HTML pdf
・ 米国の政府支援研究開発における予算算入費目の範囲と会計原則の合理的運用 HTML pdf
・ 情報先進国の情報化政策とわが国の情報技術開発における重点分野の選択指針 HTML pdf
- 1.6 平成12年度(その5) (全文)
HTML pdf
 (要旨)
HTML pdf
(要旨)
HTML pdf
- 中核的調査テーマ
技術貿易の時代に向けた米国の戦略、およびこの時代に向けた研究開発の仕組み、法・制度
- 調査の概要
21世紀のIT関連技術開発は、従来の「物の製造」から「知識の創造」へと姿を変えていく。その開発成果は、知的所有権(IPR)で権利化される。米国は、特許のカバー範囲を拡大し、ビジネスモデルやアルゴリズムなど従来は特許として認められなかったカテゴリーを特許に加えるなどの法・制度の改革や、このような特許を商品化させるため、国の支援するプロジェクトの成果を大学や企業に帰属させるBay-Dole法などを実施し、研究者の意欲をかきたてている。この結果、米国の技術輸出は大幅は輸出超過となり、その額は他国を大きくリードしている。
これに比較して、わが国の仕組み、法・制度は、箱物作りの時代に作られたままになっており、米国等と競争する上で不利なものとなっている。本調査では、わが国企業の技術貿易の時代に向けての問題意識や具体的対策、国のプロジェクトの仕組み、法・制度についての改革要望などを調べ、IPRを効率よく産み出すためのあり方を提案している。
- 関連調査テーマ
・ ハイエンドコンピューティング技術に関する調査研究Ⅱ - 高性能プラットフォーム技術を中心とする - HTML pdf
・ 人間主体の知的情報技術に関する調査研究Ⅳ HTML pdf
・ 米国政府支援研究開発プロジェクトにおけるIPR創出・取得・管理・商業化の現状 HTML pdf
・ 情報先進国の情報化政策とわが国の情報技術開発における重点分野の選択指針Ⅱ HTML pdf
・ 平成12年度調査方針の提案 pdf
- 1.7 平成13年度(その6) (全文)
HTML pdf
 (要旨)
HTML pdf
(要旨)
HTML pdf
- 中核的調査テーマ
米国のR&D計画の立案から市場創成段階までのシームレスな構造(フロントランナー構造)、およびこの構造と比較してみるわが国の研究開発の構造の問題点
- 調査の概要
米国における研究開発支援は、アイデアから基礎研究を開始する芽だし段階(上流段階)、規模を拡大していく中流段階、実用化し評価を行う上流段階、商品化し市場に投入する市場創成段階の各段階について、官産学の壁を取り除き有望な研究を連続的に支援し発展させていくシームレスな構造を作り上げている。
このために、国の研究開発を総合的に管理する組織が大統領府に作られ、連携をコントロールしている。 これにより、オリジナルな研究が芽を出し、新しい市場が生まれ、産業の新陳代謝がなされる。このような研究開発においては、大学や国研にいる研究者が、大きな役割を演じている。
一方、わが国の研究開発の官産学、および省庁間の連携を見ると、これらの組織の上に立ち、国全体のバランスや研究成果を発展させるような成果の移転のプロセスを監視し、コントロールする機構はない。近年、総合科学技術会議ができ、国全体のテーマや予算に関して影響力をもつようになったが、個々のプロジェクトの内容にまで立ち入り、統廃合を行うような権限はない。省庁間は、依然としてその間に厚い壁が存在する。
研究者の数と分布に関しても、ITについて見ると、大学・国研の研究専門の研究者は米国に比べ極度に少なく、実用化や商品に近いところまでの実証実験は、ほとんど不可能な状況である。このため、米国のような本格的な産学連携や、大学からのベンチャー起業も少ないのが現状である。
本調査は、米国のフロントランナー構造とわが国の研究開発の構造を比較し、わが国の抱える問題点を指摘している。
- 関連調査テーマ
・ ハイエンドコンピューティング技術に関する調査研究Ⅲ HTML pdf
・ 人間主体の知的情報技術に関する調査研究Ⅴ HTML pdf
・ 情報先進国の情報技術政策の動向 HTML pdf
・ 米国における最近のIT重点分野に関する調査 HTML pdf
- 1.8 平成14年度(その7) (全文)
HTML pdf

- 中核的調査テーマ
米国の連邦政府のR&D計画における省庁間の役割分担と連携の仕組み
- 調査の概要
米国の連邦政府支援の研究開発は、その上流、中流、下流から、さらに商品化、起業支援、市場創成に至るまで途切れなく続く支援の連鎖が準備されている。これを我々は「フロントランナー構造」と呼ぶこととした。この構造は、NSFやDARPAに始まり、起業支援の仕組みの一つであるSBIRでは、10の省庁が参加している。米国では、このような省庁連携が広く行われ、競争しつつも、国全体としては、新産業を起こし、産業の新陳代謝を実現している。
わが国の常識では、各省庁は、予算のぶんどり合戦や、新分野についての縄張り争い、各省庁の利益優先のふるまいをするものと考えられ、米国のような研究開発の支援の連鎖を作り出すような協力は行われないと認識されている。
では、なぜ米国では、このような省庁連携が実現されているのであろうか。本調査では、米国でこのような連携ができあがった背景やその仕組みについて、米国の元NSFの研究部長に調査を依頼するなどして、従来のこの種の調査にみられなかった結果を得た。我々が学ぶべき、省庁縦割りの弊害を乗り越えた米国の経験と英知の一端を知ることができる。
- 関連調査テーマ
・ ハイエンドコンピューティング技術に関する調査研究Ⅳ HTML pdf
・ 人間主体の知的情報技術に関する調査研究Ⅵ HTML pdf
・ 米国の連邦政府R&D計画における省庁間の役割分担と連携の仕組み HTML pdf
・ わが国IT開発拠点の中国移転に関する調査 HTML pdf
2. その他
- 2.1 Bluebook
- ・ Bluebook 2000 日本語版 (全文) pdf
 HTML
HTML
- ・ Bluebook 2001 日本語版 (全文) pdf
 (要約) pdf
(要約) pdf
- ・ Bluebook 2002 日本語版 (全文) pdf

- ・ Bluebook 2003 日本語版 (全文) pdf

- ・ Bluebook 2004 日本語版 (全文) pdf

- 2.2 AITECセミナー
- AITECセミナー 2000 - 米国の先端 IT 研究開発における合理的な運営と会計の仕組みについて -
・ セミナー報告 HTML
- AITECセミナー 2001 - 21世紀:技術貿易時代の覇者を目指す米国のIT研究開発戦略 -
・ セミナー報告 HTML
- AITECセミナー 2002 - 米国に見る産業の空洞化防止戦略とわが国の対応策について -
・ セミナー報告 HTML
- 2.3 その他
- ・ 日米比較を通して見る我が国の先端情報技術開発の問題点について(1999年9月) HTML pdf

- ・ 米国及び情報先進国における重点政策(日本学術会議50周年記念シンポジウムでの発表論文)(1999年9月) HTML pdf

- ・ PITACレポート(ITスクェアド計画を提言した大統領諮問委員会の報告)(1999年2月) 日本語版 HTML
- ・ 「21世紀のための情報技術:米国の将来に対する大胆な投資(ITスクェアド構想)」日本語版 (1999年9月) HTML
- ・ 米国におけるASCI計画、及びUltraScale Computing計画の概要 (1999年10月) HTML pdf

- ・ 米国及び情報先進国における重点政策と日本への指針 (2000年1月) HTML pdf

- ・ オーム社「エレクトロニクス」2月号の特集:日本のブレイクスルー30人の証言(2) (2000年2月)
- R&Dの新しい仕組み作りに挑む :21世紀日本繁栄の基盤をどう構築するか - 掲載原稿 HTML pdf
- ・ NTTソフトウエア(株)社内報「SO-」:鶴保社長との対談「日本における情報産業の構造的課題」(2000年2月) HTML
- ・ フランスの新ソフトウェア政策について (2000年2月) HTML
- ・ 米国の政府支援研究開発における予算算入費目の範囲と会計原則の合理的運用に関する実態調査 (2000年3月) HTML pdf
 (概要) pdf
(概要) pdf
- ・ 米国の政府支援情報技術開発における効率重視のマネージメントに関する調査 (2000年3月) HTML pdf

- ・ 先端情報技術の仕組みや法制度における日米格差とわが国が改革すべき問題点について(要約編)(2000年7月) pdf

- ・ テッキーズ・デー解説 (2000年9月) HTML
- ・ 米国特許戦略の動向と背景 (2000年11月) pdf

- ・ フランス政府における情報技術政策 (2000年12月) pdf

- ・ ソフトウェア開発事業の重点分野に関する調査Ⅲ (2002年3月) (全文) pdf
 (概要) pdf
(概要) pdf
- ・ 米国における先端的ソフトウェア研究(SDP計画)進捗報告 (2002年10月) pdf

- ・ これからのソフトウェア研究の目指すものは何か (2003年7月)
- 米国SDP 計画における研究テーマの策定ワークショップにおける議論の紹介 - pdf
- ・ NITRD グランドチャレンジ (2003年11月) 日本語版 (解説) HTML (全文) pdf

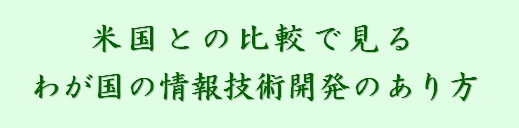
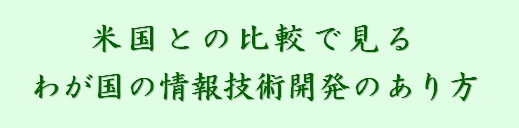








 (要旨)
HTML pdf
(要旨)
HTML pdf





 (要旨)
HTML pdf
(要旨)
HTML pdf














 (概要) pdf
(概要) pdf




 (概要) pdf
(概要) pdf


