|
| |
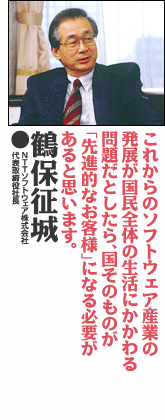
内田■米国には、国家の金を使った研究の成果は製品化して市場に出すことで納税者への利益還元になり、そこまでが政府の責任である、という確固たる国民的信念があります。アイデアの創造から開発段階の試作と評価、そしてそれを産業界に技術移転して製品化し市場を形成し、税金となって国に還流する、その資金がまた研究開発に回される、という一連のシームレスなスキームが極めてよく整備されているのです。 鶴保●日本ではこのスキームがあまりうまくできていないのが、ソフトウェア産業が立ち遅れた原因のひとつである気がします。 内田■それがまさに当研究所の主張で、私はこの問題を次のように考えています。ハードウェアの時代は、外国で完成された技術をブラックボックスとして買ってくればよかった。洋式の大砲が渡来した時、銃身内部にある螺旋状の溝の効果はよくわからなかったけれどとにかく真似して作った、というのと同じ発想です。その技術が発明された国では何度も繰り返されたであろう試行錯誤の段階をスキップできた。そして、その後は日本人特有の勤勉さやチームワークを武器に、高品質で大量生産する製造技術に磨きをかけて競争力をつけたといえます。 それがソフトウェアの時代には裏目に出てしまいます。なぜなら、ソフトウェアは日本流の製造技術によって競争力をつける余地のほとんどないものだからです。新しいアイデアを種子として試行錯誤を繰り返しながら試作したソフトウェアそのものがほとんどそのまま製品になります。 ですから、アイデアから最初の試作物を作る研究開発の上流段階を担当すべき大学や国立研究所が、国家投資の長期に渡る停滞と定員削減により弱体化し、米国のように機能しなくなってしまった日本の仕組みがソフトウェア産業立ち後れの第一の要因であると思います。 海のものとも山のものともつかないアイデアから、ある形をもった研究開発物が出来上がる。こうした上流段階は、米国では大学と国立研究所が担っています。また、その段階での成果は、パブリッシュ・オア・ペリッシュ(公開か、さもなくば滅亡か)というくらい公開原則が徹底しています。税金で開発した成果は納税者すべてに公開すべきという考えですね。研究者は公開によって名誉と研究費が得られるわけですが、これだけでは製品化へのインセンティブが弱いということで、1980年に「ベイ・ドール法」が定められ、大学などにロイヤリティの3割程度が与えられるようになりました。大学などは発明者へもその一部を与えることから、開発成果の産業への技術移転促進の大きなインセンティブとなっています。 鶴保●最近、そのような規定を盛り込んだ日本版のベイ・ドール法ができたようで、米国と同じように、大学や国立研究所の研究者に企業化優先権やロイヤリティのフィードバックを与えるのは、確かにたいへん意義のあることです。
内田■しかし、日本と米国を比較すると、その法律が適用される研究者集団の規模に天と地ほどの差があります。米国の場合、情報技術分野で学位をとる人が年間約2000人いると言われています。日本は300人程度。米国の国立研究所には12〜13万人の研究者がいます。このうち20〜30%が情報技術の研究に携わっているといわれています。日本では、すべての国立研究所を合わせて、多めに見積もっても150人くらいの研究者しかいません。日米の人口比を考えても、この差は大きいと言えます。また、米国の大学では、学生を教える義務のない研究専門の研究者が約2000人いるのに対し、日本の大学ではそのような立場の人は非常に稀です。 |
| 3/6 |