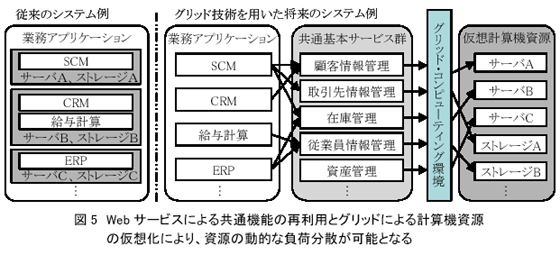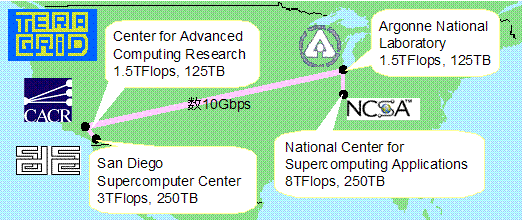
第3章 ハイエンドコンピューティング研究開発の動向
関口 智嗣 委員
1. はじめに
平成15年3月4日から7日にかけて第7回グローバルグリッドフォーラム(GGF7)が東京・新宿京王プラザホテルにて開催された。総勢約800人、海外から500名もの参加を見た当会議はアジア・太平洋地区では初めての開催となった。
これらをきっかけに新聞、雑誌、Webニュースなどのメディアを通じても、グリッド・コンピューティングという言葉を良く見かけるようになってきた。大学・公的研究機関などの大規模な計算機システムが対象となるばかりではなく、一般家庭のパソコンを対象としたグリッド技術が構築されてきている。元来は、科学技術計算の分野で始まったグリッドの波であるが、徐々にビジネスの世界に押し寄せてきている。すなわち、科学技術における応用としてはバイオインフォマティクス、創薬デザイン、ライフサイエンス、高エネルギー物理や天文観測などの大規模科学実験などが知られていたが、今後はWebサービス、ユーティリティ提供、アミューズメントなどが次のターゲットと考えられている。こうした大きな構想とは別に、現実の問題としてグリッドをどうすれば毎日の研究生活に使えるようになるのか、そうした日々のグリッドを作るためにはなにが必要なのかを念頭に置きながら、技術の現状を整理し、今後のグリッド技術動向全般について概観する。
グリッドとは、「遊休PCをネットワークで繋いだもの」でもなければ、「スーパーコンピュータをネットワークで繋いだもの」でもない。新たなネットワークを利用した技術として、安全に・安定して・安易に様々な情報サービスを享受できるようにするための技術である。「安全に」とはセキュリティ面での配慮があること、「安定して」は必要な計算資源、記憶資源、ネットワーク資源が必要なだけ提供されるように計算資源が仮想化されていること、「安易に」とはユーザは特に端末の裏側で何が起きているか気にする必要なく情報サービスへのアクセスを可能とすることを目指している。
グリッドを大きく分類すると図1のように考えられる。ここでは、PCを中心としたいわゆる分散計算型のグリッドと、狭義のグリッドとして、柔軟な情報サービスを目指したものがある。こちらは、ビジネスグリッド、コンピューティンググリッド、データグリッドなどの主な目的に応じた分類が可能である。しかし、これらの境界は曖昧であり、明確な分類ではない。通常は複数の目的を同時にひとつのシステムとして実現される。
図1 グリッド技術の分類
グリッド・コンピューティングの考え方そのものは、十年以上前から芽生えていたが、実用的な例題に活用され始めたのは科学技術分野においてさえ、ここ数年のことである。大学、研究所などのスーパーコンピュータを高速ネットワークで接続し、大規模なグリッド環境を構築する試みが世界各地で進められている。米NSFの基金によるTeraGridは、カリフォルニア州にあるSDSC、イリノイ州にあるNCSAなど四つのデータセンターを、高速伝送網で接続するプロジェクトである(図2参照)。光ファイバー通信で異なる波長の光信号を複数のチャネルで伝送するWDM (wavelength division multiplexing)通信方式を用い、将来は50-80Gbps(1Gbpsは1秒間に109ビットを転送)を目指す。各センターにはItanium2による大規模なLinuxクラスタとRAID装置を配備し、トータルで13.6TFlops(1TFlopsは1秒間に1012回の浮動小数点演算を実行する性能)の演算性能と450TB(1TBは1012バイトの容量)のストレージを有するグリッド環境を構築する。
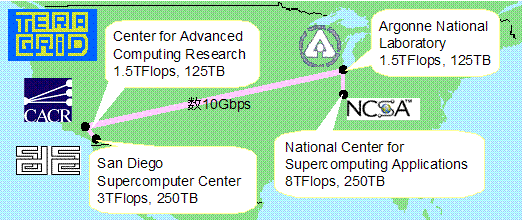
図2 米国TeraGridプロジェクトとして計画中のグリッド環境
2. 海外における動き
グリッド・コンピューティングの世界は、2002年になってから急速な展開を示している。2002年2月にカナダのトロントで行なわれたグリッド技術の標準化を進める国際会議Global Grid Forum(GGF)4において、米IBM社がグリッド基盤の新しいアーキテクチャとして、Webサービス技術を取り込んだOGSAを発表したことが要因の一つである。
GGFは、1999年に米国を中心に始まったGrid Forumにヨーロッパ、アジア諸国が加わり2000年11月組織された世界レベルの標準化団体である。GGFには表1に示すように7つのエリアがあり、エリア毎に設置されたワーキンググループ(WG)とリサーチグループ(RG)が主な活動である。WGは仕様書、ガイドライン、推奨事項といったドキュメントの提供を目指し、非常に特定の技術に焦点を当てている。RGはドキュメントを作成するには時期尚早なテーマについて、長期的に議論を進めている。この会議は年に3回の頻度で会合が行われており、2002年7月に第5回目の会議GGF5がスコットランドのエジンバラで開催された。図3に示すように、GGFへの参加者数はGGF4から急速に増加し、グリッドへの関心の高さを示している。OGSAの提案が、今回企業から多くの参加者を得て急増した理由の一つと考えられる。
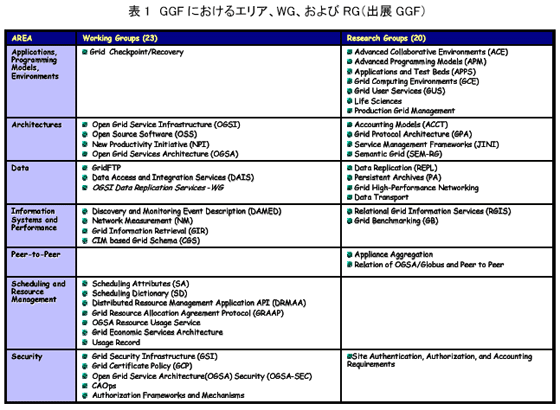
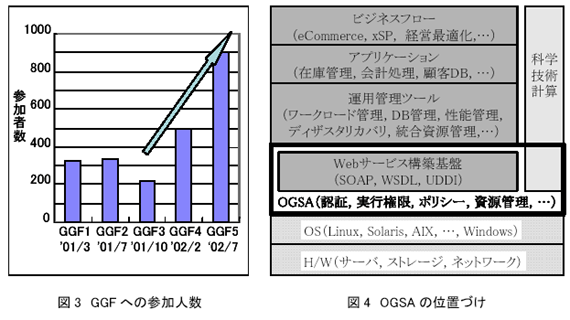
OGSAはグリッドとWebサービスの良い点を統合したコンセプトであり、J2EEや.NETなどを用いるビジネス分野との親和性が高い。SOAP、WSDL、UDDIなどのWebサービス技術を用いて、グリッド基盤を構築することにより、ビジネスでの情報システム利用が、科学技術計算と同じ基盤上で実現されるようになる(図4参照)。その実現のためには様々な仕様拡張が必要である。例えば、計算機資源の仮想化を行うには、実行されるサービス(アプリケーション)が特定の計算機資源に留まることを前提にはできない。すなわち、サービスの一時的な生存を可能にしなければならず、サービスを記述するWSDLにサービスの生成・消滅・生存時間などの仕様追加が必要となる。このようなグリッド向けの拡張仕様をGSDLしてGGFのOGSI-WGなどで検討されている。
OGSAのミドルウェアへの実装については、主としてGlobusプロジェクトで進められている。Globusプロジェクトは、米国アルゴンヌ国立研究所と南カリフォルニア大学を中心に、米国の大学、IBM社、マイクロソフト社といった企業も参加する最も大規模なミドルウェア開発チームである。GGFと並行してグリッドミドルウェアGlobus Toolkitを開発し、ある種のデファクトスタンダードとなっている。
Globusが提供するのは、資源管理、資源情報サービス、データ管理の機能といった、グリッドにおけるプリミティブな機能である。これらの要素サービスを束ねて、ワークロード管理、データベース管理、ディザスタリカバリー、性能管理、統合資源管理などを提供するのが、上位の管理ツールである。しかし、管理ツールレイヤーにおける標準化についてはまだ手がつけられていない。
3. ビジネスにおけるグリッド技術の応用
OGSAがビジネス分野でも使われる基盤であることは既に述べた。では、具体的にどのように利用されるのか。現在のグリッド技術、およびWebサービス技術と融合した将来のグリッド技術を用いることで、どのようなビジネス形態が現れるかを述べる。
企業情報システムの仮想化が現時点で容易に実現可能な利用方法である。企業における計算機資源は、一般に平日の夜間や休日などを合わせると50%以上は休止状態であり、ロードバランスも不均一になり易い。グリッド技術を用いて計算機資源を仮想化・統合化することにより、業務アプリケーションの実行効率をあげることができる。ユーザは使用するマシンを意識する必要はなく、投入されたアプリケーションジョブは資源の空き状況に応じてスケジューリングされ、効率よく順次実行される。このようなグリッド環境を構築するためのミドルウェアは、研究ベースとしてはGlobusプロジェクトによるGlobus Toolkit、UNICOREプロジェクトによるUNICOREなどがある。またプラットフォームコンピューティング社、アバキ社、エントロピア社などからもツールやソリューションが提供されており、車体設計を行う自動車メーカーやリスク管理評価を行う金融機関など多くの海外企業で利用が始まっている。
一方で、Webサービス技術の登場によりアプリケーションを連携・統合することが可能となった。共通的な要素機能としての顧客情報管理、取引先情報管理、在庫管理、従業員情報管理、資産管理などをSOAP、WSDLを用いてサービス化し、SCM、CRM、ERP、給与計算などの業務アプリケーションから呼び出すように再構築できる(図5参照)。要素機能を再利用することで、業務システム開発の工数が削減可能である。将来OGSAとして、Webサービス技術がグリッドの基盤として確立した後には、各業務アプリケーションを実行するサーバを固定する必要がなくなり、負荷状況に応じて必要なサービスを空いているサーバ上に起動、相互に連携実行させることが可能となる。ITへの投資削減を進める企業にとって、グリッド技術は資源を有効活用する重要なツールとなるだろう。
また、グリッド技術を用いて統合・仮想化された計算機資源に対して、必要な時に必要なアプリケーションを起動して利用することは、電気、ガス、水道と同様にユーティリティの一つとして見なすことができる。米IBM社は、「e-business on demandTM」のコンセプトを掲げユーティリティ事業に乗り出している。このサービスの基盤として7月に発表した「Linux Virtual Services」では、同社zSeriesで構成したLinux搭載メインフレームを仮想サーバとし、各顧客の要求に応じて資源を割り当てる。ユーザは必要な分だけの処理能力を買うことができる。まさしくユーティリティ事業である。
ヒューレット−パッカード社は、コンパック社との合併で強化されたグリッド技術により、ユーティリティデータセンター(UDC)のソリューションを提示している。UC(Utility Controller)ポータルを用いて、ビジネスに合わせたサービス設計とシステム構築のテンプレート記述を行うと、UCソフトウェアがUDC内にプールしてあるクラスタ資源を適切にネットワーク接続し、必要なアプリケーションをインストールする。ビジネスの立ち上げがフレキシブルに且つ短期間に実施可能である。
分散リソース管理ツール「Sun Grid Engine」とWebサービスのフレームワーク「Sun Open Net Environment(Sun ONE)」の統合を行ってきたサン・マイクロシステムズも、ユーティリティコンピューティングを実現する次世代データセンター構想をこの9月に発表した。ネットワークコンピューティングのアーキテクチャ「N1」を発展させ、自ら新しい事業を起こす決意である。