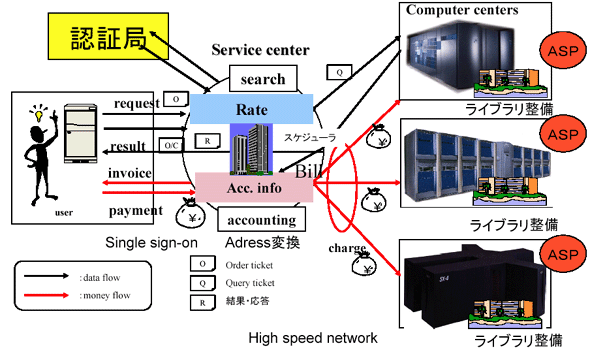
第3章 ハイエンドコンピューティング研究開発の動向
4. ビジネス応用への課題
ユーティリティ事業にまで至るグリッド技術のビジネス応用実現にあたっては、まだまだ多くの課題が残されている。特に、ミッションクリティカルな分野への応用となるため、システムの安定稼動、セキュリティ、相互運用性といった課題が重要である。また、ユーティリティとして普及・浸透するためには、技術的課題の他にも、十分な数の利用者が参入すると、サービス提供者の格付け、利用者の与信、利用しやすいビジネスモデルとそれに適した課金システムなど、解決すべき社会的課題も多い。
システムの安定稼動に向けては、具体的な活動が始まっている。要求されたアプリケーションの実行時に、プロセッサやメモリなどのハードウェア資源を必要な量確保できなければ、処理性能の低下が生じる可能性がある。また、ハードウェアの一部に障害が発生した場合、人手による修復を待っていたのではビジネスチャンスを失う可能性がある。IBM社は早い段階からサーバの自律機能を強化するプロジェクトeLizaを進めている。処理能力が低下したら、アプリケーションを停止することなく自動的にプロセッサやメモリを追加する。障害が生じたら、システムが自動的に障害を検知して修復を行う。自律機能の一つである動的資源配置を、NECはNX7000/superdomeの同一筐体内を対象に、ミドルウェア「HA/GlobalMaster」として製品化した。ヒューレット−パッカード、サン・マイクロシステムズ、富士通なども同様の機能実現を計画している。これらシステムの自律機能は、ビジネスへのグリッド技術利用において重要な要素である。
ハード資源の統合・仮想化を行うことは、異なるユーザが資源を共有する可能性があることを示している。ユーザの認証、資源の制御、情報の改ざん/漏洩防止などセキュリティ上の課題解決はビジネス上特に重要である。
セキュリティについては、これまで既存の技術の流用を基本としてきた。例えばGlobusでは、GSIと呼ばれるSSLをベースとした認証機構で実現している。Globus独自の第三者認証機関CAを運営しており、全てのユーザにSSLで用いられるX.509の証明書を発行している。また、グローバルIDとローカルIDとの対応表による利用可能な資源の制限といった方法が用いられている。
GGFでは、インターフェースやプロトコルについてガイドラインを設けるだけで、具体的なツールや技術については規定していない。現在は、どうやってCAを信用するか、異なるユーザIDで複数の資源にアクセスする必要がある場合の管理方法など、について議論している。
ビジネスの世界では、様々な組織階層が存在し、それらの間で開示可能な情報は様々に異なる。従って、グループ内、企業内、提携企業間、無制限公開など、資源を共有する範囲によってセキュリティのレベルを変える必要がある。
また、初めての利用者や初めてのアプリケーションを迎え入れる場合、どうやって相手を信用するか、逆にサービス提供者の信用を利用者に与えることも重要な問題である。利用者の与信、提供者の格付け、アプリケーションが当該プラットフォームで稼動しウィルスなどを内包していないことの保証、などを行う第三者機関の存在が必要である。
オープンなシステムの世界では、相互運用性は欠かすことのできない課題である。オープンソースであるLinuxによるクラスタシステムは、コストパフォーマンスの面だけでなく、プラットフォームの均一化が図りやすいという面からも、グリッド環境構築に採用され易い。しかし、その他のプラットフォーム(ハードウェア、OS、ミドルウェア含む)を提供するハードおよびソフトベンダーも多く、ヘテロな環境に対して稼動することは必須の条件である。例え仕様が標準化されようとも、実装したツールが連携できるとは限らない。
ビジネスの世界でグリッド技術が花開くのは5年先とも言われているが、早期実現を目指して、これらの課題解決に向けた研究開発が世界各国で進められている。
5. 使えるグリッド
「使えるグリッド」を構築するためには、一般のユーザがどのようなことをグリッドに期待しているか十分な調査が必要である。グリッドに期待されるものとして、複数のサイトのコンピュータを同時に利用して、大規模な計算を実施するというものがある。しかしながら、その「使える度」は下記のようなものであった。これは米国
AVAKI社の CTOである Andrew Grimshaw氏がバイオインフォマティクス関連の市場調査を通じて整理したものであり、同様な傾向は筆者がCBI学会において講演中に問いかけた回答でも確認された。
確かに、研究の最先端としては複数サイトを利用して大規模計算を実現するというグランドチャレンジを一部の先進的なユーザは想定している。しかし、これはむしろ限定されたシナリオと考えられる。ユーザの多くはグリッドによりいかに日々のコスト(TCO)削減に結びつくかが導入あるいは使用に踏み込むきっかけと考えられる。このような、日々使えるグリッドを作って行く必要がある。逆説的であるが、グリッドを使っていることをユーザがいかに意識しないで済ませるかが必要となる。
我々は JSTの計算科学活用型プロジェクトの課題としてGridLib という仮想スーパーコンピュータセンターの実現を目指している。これは日々のグリッドの例としてユーザが計算サービスを提供する機器に関してOS、機種、ライブラリ、関数、ライブラリ毎のインターフェース、異なる運用ポリシー、スケジューリング、などの違いを隠蔽することが可能となる。具体的にはGSI
(Grid Security Infrastructure)と Grid RPC 技術を用いることで実現を目指している。図6にグリッドASPのイメージを示す。現在は、ASPの例として量子化学計算用ソフトウェア
GAUSSIAN, 熱流体コード PHENICS、構造解析コード NASTRAN 等を対象としている。GAUSSIAN は Quantum Chemistry
Grid の一環としてすでに産総研・先端情報計算センターにおいてユーザに公開を始めたところである。
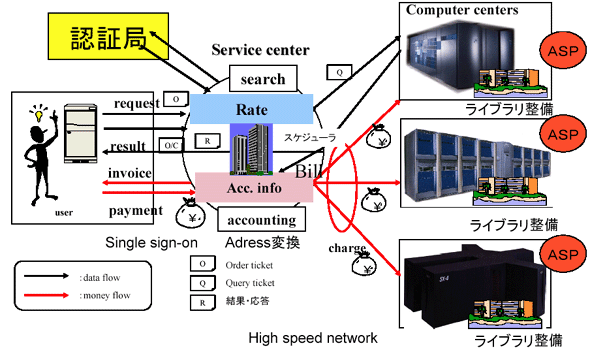
図6 グリッドASP
6. おわりに
グリッド技術はインターネットの急速な普及をもたらしたアクセス技術の整備とバックボーン技術の高速化、高信頼化が前提となっている。一方で、コンピュータのサービス提供技術はメインフレーム集中型モデルからクライアント・サーバ型モデルを経て、オープン型へとネットワーク技術の変遷とともに推移してきた。グリッド技術の根幹は仮想的な組織における資源共有の実現であり、これを活用した新たなサービスモデルにより現状のサービスが「グリッド化」されてくる。例えば、将来Webサービス技術がグリッドの基盤として確立した後には、各業務アプリケーションを実行するサーバを固定する必要がなくなるため、負荷状況に応じて必要なサービスを空いているサーバ上に起動、相互に連携実行させることが可能となる。ITへの投資削減を進める企業にとって、グリッド技術は資源を有効活用する重要なツールとなることが期待される。今後、グリッド技術は情報基盤技術として当然のように産業基盤となる科学技術計算の分野ばかりではなく、ITビジネスにも広がってくる。応用範囲が拡大するにつれ、多くのベンダーが事業に参入してくるであろう。競争と協調、がグリッド技術の今後の課題である。