
DARPAは2002年より”High Productivity Computing System”(高生産性コンピューティング・システム:HPCS)プログラムを開始した。
第2章 米国のハイエンドコンピューティング研究開発動向
(1)DARPAの”High Productivity Computing System”プログラム 
DARPAは2002年より”High Productivity Computing System”(高生産性コンピューティング・システム:HPCS)プログラムを開始した。
本プログラムは2010年までの9年間にわたる長期計画であり、現在のコンピュータシステムと、製品化がまだ当分先と言われている量子コンピュータとの間のギャップを埋めるものと位置づけられている。計画はフェーズ1(概念研究:1年)、フェーズ2(R&D:3年)、フェーズ3(大規模開発:5年)に分かれている(図2.4参照)。フェーズ1についてはBAA(Broad Agency Announcement)により企業や大学からの提案が公募され、CRAY、IBM、SGI、Sun等の企業が提案を行っている。以下にHPCSプログラムの生まれた背景とその目的について記す。
1)背景
2)目的
3)プログラム計画
図2.4に本プログラムの計画を示す。
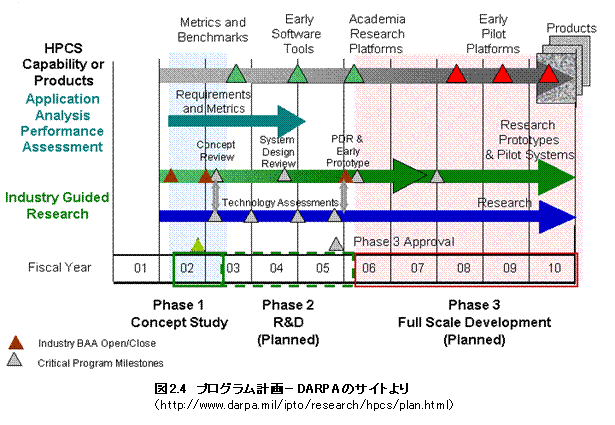
(2)量子コンピュータの研究動向
量子コンピュータの実用化は数十年先(20年以内から50年以上まで種々の意見がある)と言われている。ドッグイヤーと呼ばれる近年のITの進展速度からすれば、はるか遠い未来の話と言ってもいい(このことを考えれば、前述のHPCSプログラムのようなものが生まれてくるのもうなずけることであろう)。しかし、米国政府はこの遠い将来の実用化に向けて、金額的にはまだそれほど大きくないにしても、この10年間継続して着実に研究支援を行ってきている[4]。
以下に米国連邦政府の資金による主要な量子コンピュータ研究プログラム(公募)および政府機関における研究の一部を挙げておく。
その他、Caltech、Stanford、MIT、UCBなど多くの大学でも研究が行われている他、民間企業ではIBMの活発な研究が目立っている。
また、日本においても政府系研究機関や富士通、NECなどの民間企業でも研究が行われ、米国と対等な成果を出しつつある。
参考文献
[1] NR. Adiga, et al.: “An Overview of the BlueGene/L Supercomputer”
http://sc-2002.org/paperpdfs/pap.pap207.pdf[2] Creating Science-Driven Computer Architecture: A New Path to Scientific Leadership - A Strategic Proposal from ANL and LBNL−, pp.31-36, Oct. 2002
http://www.nersc.gov/news/ArchDevProposal.5.00.pdf[3] 関口智嗣, “Gridによる世界戦略とブロードバンドコンピューティング技術”
ハイエンドコンピューティング技術に関する調査研究II, 先端情報技術研究所(2001)
pp.42-43, 2001年3月[4] 総務省, “21世紀の革命的な量子情報通信技術の創生に向けて”, 2-5-1, 2000年6月
http://www.yusei.go.jp/policyreports/japanese/group/tsusin/00623x01.html#20
(石井 英志 幹事)