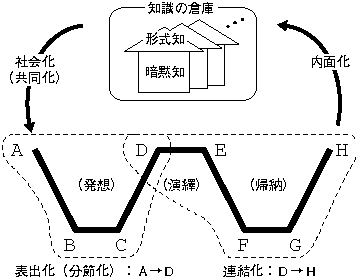
3.8 知識創造プロセスとその支援環境
3.8.1 知識創造プロセス
パース[米盛81]によると、19世紀までの二千年近くの間、学問の正当な方法論は演繹のみであった。しかしながら彼によって、帰納および発想の方法論が人間の問題解決・推論の方法論[米盛81,國藤87]の中に位置づけられた。同時にイギリス経験学派によって、20世紀前半に帰納法の数理科学的基盤が創られた。またKowalski教授を中心とする論理プログラミング一派[Kowalski79, Kakas92]によって、今日漸くアブダクション[國藤87]の論理的基盤が整備され、それに基づくプログラミング言語[Kakas92, 金井97]も実装されるようになった。アメリカ・プラグマティズムの良き伝統を引き継ぐサイモン[サイモン69, 89]を中心とする意思決定の科学も、問題の発見、代替案の生成、代替案の選択、過去の決定の再検討というプロセスで捉えており、発想・演繹・帰納というプラグマティズムの枠組みを越えている訳ではない。
ところが川喜田[川喜田67, 70a, 70b, 87]、野中[野中90]は上記の立場に飽き足らず、人間の問題解決・推論の後処理の局面にも焦点をあて、知の創造プロセスをそれぞれW 型累積KJ法、知のスパイラル理論として展開した。ポラニー[ポラニー80]は名著「暗黙知の次元」の中で、知識を形式知と暗黙知に分類し、前者は人間の知識の総体から見ると氷山の水面上の部分しか過ぎないことを主張した。これを受け野中[野中90]は、知の伝達過程 に注目し暗黙知から形式知への変換を分節化(表出化)、形式知から形式知への変換を連結化、形式知から暗黙知への変換を内面化、暗黙知から暗黙知への変換を社会化(共同化)と呼んだ。この立場によると、上記問題解決の発想のプロセスは分節化、演繹・帰納の立場は連結化のプロセスに相当する。内面化、社会化のプロセスは組織・社会においてはそれぞれ教育、実戦体験として組織的・社会的「知の伝承」プロセスの中に埋め込まれていると見ることができる(図3.8-1)。
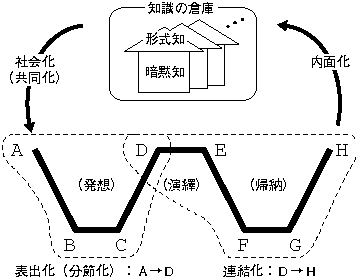
図3.8-1 W型問題解決学と知識スパイラル
近年、情報革命、デジタル革命あるいは知識革命の進展により、上述の内面化、社会化の役割の重要性が見直されつつある。コンピュータを人間・グループ・組織・社会の問題解決・推論のための支援ツールと見る我々の立場からすると、発想支援ツールの研究[國藤98a, 98b]はまさに分節化支援ツールの研究開発を志向しており、従来から行っているコンピュータシステムの研究は連結化支援ツールの研究開発に相当する。それでは、形式知を暗黙知に変換する内面化の過程、暗黙知を暗黙知のまま伝承する社会化の過程を支援するコンピュータシステムの研究開発は可能であろうか。本小論では、人間・コンピュータ複合体で内面化支援ツールや社会化支援ツール[國藤97]の実現に接近する研究開発シナリオを知識創造方法論[國藤98c]として述べる。
3.8.2 知識創造支援方法論
3.8.2.1 発想を促す分節化支援ツール
暗黙知を特徴付ける概念に、非言語知、包括的な知、経験知、身体知、共時的な知、アナログ的な知、主観的な知がある。また形式知を特徴付ける概念に、言語知、分析知、合理的知、時系列的な知、デジタル的な知、客観的な知[ポラニー80,野中90]がある。ポラニーは「暗黙知とは我々が語ることができるよりも多くのこと知っている」[ポラニー80]と言明しているように、暗黙知と形式知はそれぞれ氷山の水面下の部分と水面上の部分で抽象的に説明される。これを受け、野中[野中90]は日米の組織風土の違いを明らかにし、日本的組織風土の長所をも顕在化した。
人間の持っている膨大な暗黙知から形式知を取り出す分節化のプロセスを支援する発想支援ツールを実現するには、筆者によって指摘されたように発散的思考、収束的思考、およびアイデア結晶化のプロセスを支援するツール[國藤93]を構築する必要がある。例えば、拙研究室ではブレインストーミング支援ツール[藤田97]、テキストマイニング[野口97]やバネモデル[高杉96]に基づく発散的思考支援ツール、および複数の図解の共通部や差異部を可視化表示[女部田96]する収束的思考支援ツールの研究を行っている。
3.8.2.2 知の結合・検証のための連結化支援ツール
パースによればこのプロセスは演繹と帰納(仮説検証)からなる。発想支援ツールの使用によって創造されたアイデア(代替案)は演繹的な連結化支援ツールである各種の意思決定支援グループウェア[加藤97, 98]によって、主観的かつ客観的にどのアイデア(代替案)を選択すべきかが決定される。さて問題は帰納的な連結化支援ツールの役割である。この段階の本質は「仮説検証」であり、発想支援ツールで生成された仮説としての知識表現のレベルによって、様々な仮説検証法[米盛81,國藤87,ポパー80]が考えられる。我々はそれを説明可能性に基づく検証、論理的証明に基づく検証、因果的説明に基づく検証、統計的予測・シミュレーションに基づく検証(図3.8-2)、等に分類することができる。
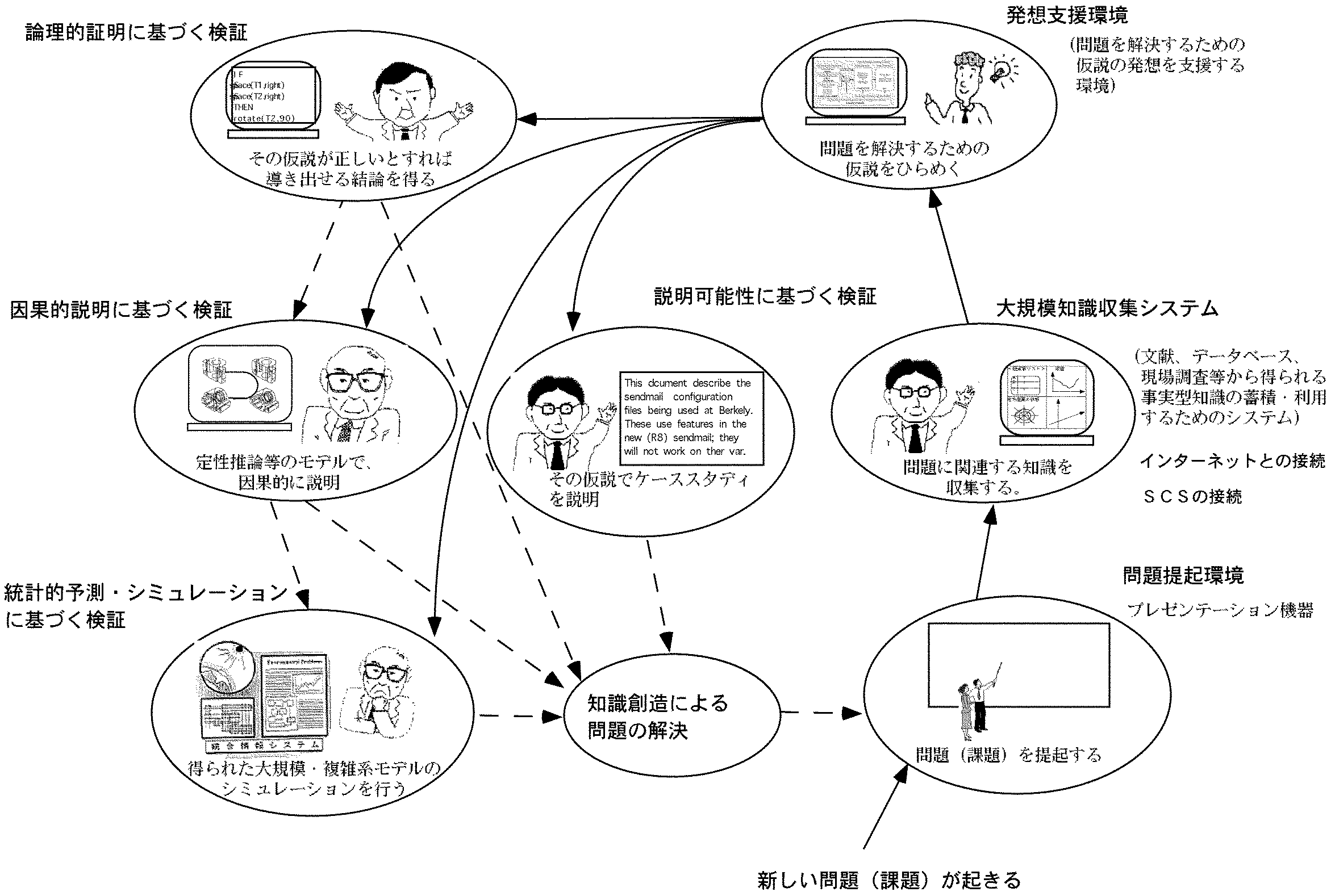
図3.8-2 検証の諸相に注目した知識創造プロセス
3.8.2.3 知の整理・同化のための内面化支援ツール
内面化という知識変換モードでは、行動・実戦を通じた形式知の体得やシミュレーションや実験による形式知の身体知化が行われる。また社会化という知識変換モードでは、社内外の歩き回りによる暗黙知の獲得、暗黙知の蓄積・伝授・転移が行われる。ピアジェ心理学[ピアジェ 72]でいうシェーマの同化プロセス、シェーマの調節プロセスを個人からグループ・組織・社会に展開したのが内面化、および社会化(共同化)である。このような内面化のプロセスを支援するツールを我々は内面化支援ツール、社会化のプロセスを支援するツールを社会化支援ツールと呼ぶことにする(図3.8-3)。
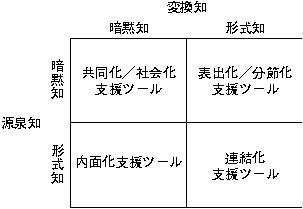
図3.8-3 知識スパイラル[野中 90]から見た知識創造支援ツール
形式知の暗黙知への変換は通常、教育やオンザジョブトレイニングを通じて行われるが、基本的に人間の頭脳という暗黙知の器への形式知の同化というプロセスで行われる。内面化による形式知の獲得は矛盾した知識も系統的に知識として吸収し、言語知のみならず視覚、聴覚、触覚、嗅覚からの「知」をも知識変換、知識同化していき、より深い知の体系となって身体知化される。従って、このようなプロセスをサポートするツールはアイコンタクト[石井 94]の取れる高品質のマルチメディア臨場感双方向通信システム[宮原98a, 98b]上で実現されるであろう。
3.8.2.4 知の伝承・調整のための社会化支援ツール
暗黙知から暗黙知への変換は通常、現場や顧客と共通体験する中で知識が伝達されていく。基本的にある人間から別の人間への暗黙知の伝承というプロセスで行われる。ここでの伝承のトリガーは暗黙知全体の矛盾の発生であり、この矛盾を感性として素早く気づく能力である。この気づきを支援するには、臨場感溢れる知識創造環境を提供し、存在そのもの、動作そのものを気づかせる各種アウェアネス環境[山上93, 門脇98, 99]、あるいは、雰囲気、熱意、気を伝える臨場感溢れる知識創造環境を提供しなければならない。我々は既に知識アウェアネス[門脇98]、WWW アウェアネス支援ツール[中川98]を構築し、このような気づきを組織的に支援するツールを構築しつつある。また仮想空間内にオフィスに在勤しているかのようなアウェアネス情報を提供する試みも既に成されている。従って、このようなプロセスをサポートするツールは各種感覚からのセンサ情報をも自然に伝える高品質双方向臨場感通信環境、すなわち限りなきフェースツーフェースに近い知識創造環境として実現されるであろう。このような研究の一つとして注目される研究にMIT 石井のタンジブルメディア[石井97,石井98]がある。
3.8.3 知識創造支援ツール
3.8.3.1 分節化支援ツールの実例
発想支援ツールや創造性支援システムの研究として、近年、日本を中心に米国や英国の先端的研究者がこの領域の研究開発を立ち上げている。
この分野は、コンピュータが人間の創造的な問題解決活動を支援する『発想支援システム』という一大研究領域として、その研究開発[富士通研91,電子協92,國藤研92, 94,國藤93,計測自動95a, 95b, 97,人工知能96]が着実に前進しつつある。我々は発想支援システムの研究開発を行うにあたって、近い将来において実現可能なあらゆる技術を駆使して、人間の創造的問題解決プロセスを支援するシステム構築を念頭におき、人間の創造的思考が発散的思考のプロセスと収束的思考のプロセスからなることに注目した。それらの支援機能の実現をツール化したものが多いことから、我々は発想支援ツールを発散的思考支援ツール、収束的思考支援ツール、統合型思考支援ツールに分類した。人間の思考・発想のプロセスが、上記プロセスからなり、かつそれらにおいてアナログ情報処理、デジタル情報処理が相互に寄与していることに着目し、実際にそのようなシステム構築の事例・構想を、ここ十年間に渡って調査した。その結果、国内の代表的システムの研究者を一堂に会したシンポジウムが毎年開催[富士通研91,電子協92,國藤研92, 94,國藤93,計測自動95a, 95b, 97,人工知能96]されるようになり、学会誌の特集[國藤93]や関連国際会議[Jain98]の勃興、関連プロジェクトの興隆が見られるようになってきた。
その際最も興味深かったのは、日本においては(KJ法を中心とするボトムアップ的な)収束的思考支援ツールに優れたものが多く、逆に欧米においては発散的思考支援ツールに斬新なものが多かったという事実である。ここ数年の研究開発動向を要約すると、『コンピュータの得意なことはコンピュータに、人間の得意なことは人間にまかす』工学的アプローチが最も将来性のある研究開発戦略であることを実証している。発想支援システムを構築しようとする場合、発想のアウトプットを生成するツールの構築は「計算量の壁」の問題から言っても原理的に困難であり、発想のプロセスを支援するツールの構築が生産的である。次のような発想支援システムが注目されている。
発散的思考支援システム: Keyword Associator(富士通研)、Articulation Assistant 0/1(東大)、SC0/SC1(東大)、インスピレーション(アップル)、AIDE(ATR)、Wadaman(阪大)
収束的思考支援システム: KJ-Editor(慶応大)、CONSIST(電力中研)、群元(阪大)、e-KJ法(川喜田研)、Colab(Xerox Parc)、FISM(北大)、Grape(富士通研)、D-Abductor(富士通研)、D-Mergin(北陸先端大)、Group Navigator I/II(北陸先端大)
統合型思考支援システム: Intelligent Pad(北大)、GrIPS(富士通研)、DEFACTO(電通)、Pizza(富士通研)
このような先端的なツールを、オフィスの知的生産性向上に役立てようという試みが随所で行われ、実際意思決定の知的生産性が3-5 倍上がったという報告[加藤97]がされている。コンピュータの究極の進化形態は、人間の知的生産のツールである発想支援システムである。あなたの企業が協調と分散の時代である21世紀のリーディングカンパニーになるには、新しい集団問題解決(組織的意思決定)のツールである発想支援システムの活用に習熟しなければならない。
3.8.3.2 連結化支援ツールの実例
従来から理工学の世界ではあらゆる知識を0,1のデジタル情報に変換し、知識をあるデジタル情報化された知識表現から別のデジタル情報での知識表現に変換するプロセスの中で、仮説からの演繹、それに基づく仮説の検証を行っている。従って、伝統的な仮説からの推論、仮説の検証に関するツールは枚挙にいとまがないほど存在し、既存のコンピュータ技術はまさにデジタル情報上の形式知を変換する連結化支援ツールと言える。
3.8.3.3 内面化支援ツールの実例
内面化支援ツール、社会化支援ツールを構築する場合、W型KJ法でいう「知識の倉庫」(図3.8-1)として何を前提としてツール化するかによって、その支援すべき機能が異なってくる。従来この「知識の倉庫」は個人の知識、小集団の知識、組織の知識、社会の知識として蓄積されてきた。紙という文明の利器の発明以来、形式知である文字が重宝され、暗黙知を格納可能な人間の頭脳のもつ潜在的能力が徐々に軽視されるようになった。そこに計算機の登場とともに形式知の進化系であるデジタル情報が文字情報、音声情報、画像情報、そして手書き絵文字情報の領域を浸食するようになり、それとともに内面化支援ツール、社会化支援ツールの構築法も異なってきた。本論文では、デジタル情報として蓄積可能な形式知を人間という身体のある生物のもつ五感のもつアナログ情報として蓄積可能な暗黙知に変換するプロセスとしての内面化、社会化を支援するツール体系を考えることにする。
人間とコンピュータのインタフェース研究においては、如何にして対面環境に近いインタフェースを提供するかが研究課題のひとつである。標準的には高解像度、高音質の高品質AV機器を用いた双方向通信システムを開発すればいいと言われている。ところが「熱意、力強さ、誠実さ、自信等に関して、相手はどこで判定しているか」に関する心理学的実験によると、バーバル情報は高々7%、音声情報は38%、ノンバーバル情報は55%という実験結果が出ている。すなわち、音声・画像以外の情報がコミュニケーションにはおおいに寄与している。そこで双方向通信システムに対面環境に近い臨場感を付与する新しい環境を構築するには、どのようにするかが、次なる研究課題である。この方向に対して宮原は「未来映像音響創作と双方向臨場感通信を目的とした高品位Audio-Visual System の研究」を行い、いわゆるデジタル臭い音の原因が、時間伸び縮み歪みである[宮原98a, 98b]ことを明らかにした。この結果は、高度感性情報の再生に「生演奏には所詮及ばない」という諦めを打破し、深刻さ、凄み、胸にしみ込む等の高度の感性に訴える音を再生する新世代オーディオの設計法を示唆しつつある。
3.8.3.4 社会化支援ツールの実例
我々はこの課題克服に対して、視線の一致、相手の存在や動作の気づき、情報の存在の気づきを配信できる各種アウェアネス環境の構築が社会化支援ツールを構築する第一歩であると考えた。そこでアウェアネスの分類から、社会化支援ツールへの接近を述べる。
ゲイズアウェアネス:石井の Clear Board の研究[石井94]は一貫してアイコンタクトの取れる情報環境を提供しようというものである。視線の一致の取れる情報環境の構築の研究は多い。
遭遇アウェアネス:コミュニケーションの開始にきっかけを提供するというアウェアネス研究は松下に始まり、松浦[松浦94]や石田[石田98]の研究に引き継がれている。
知識アウェアネス:山上[山上93]によって提唱され、組織に眠っている膨大な形式知である組織知の存在を気づかせるシステムへと発展したのが門脇の情報取得アウェアネス研究[門脇98]である。
WWW アウェアネス(図3.8-4):ネットワーク経由であるWebのホームページを誰が見ているか、どこを見ているか、どのように注目しているかのアウェアネス情報をマシン、OSフリーで情報提供しようというのが、中川のWARP[中川98]である。
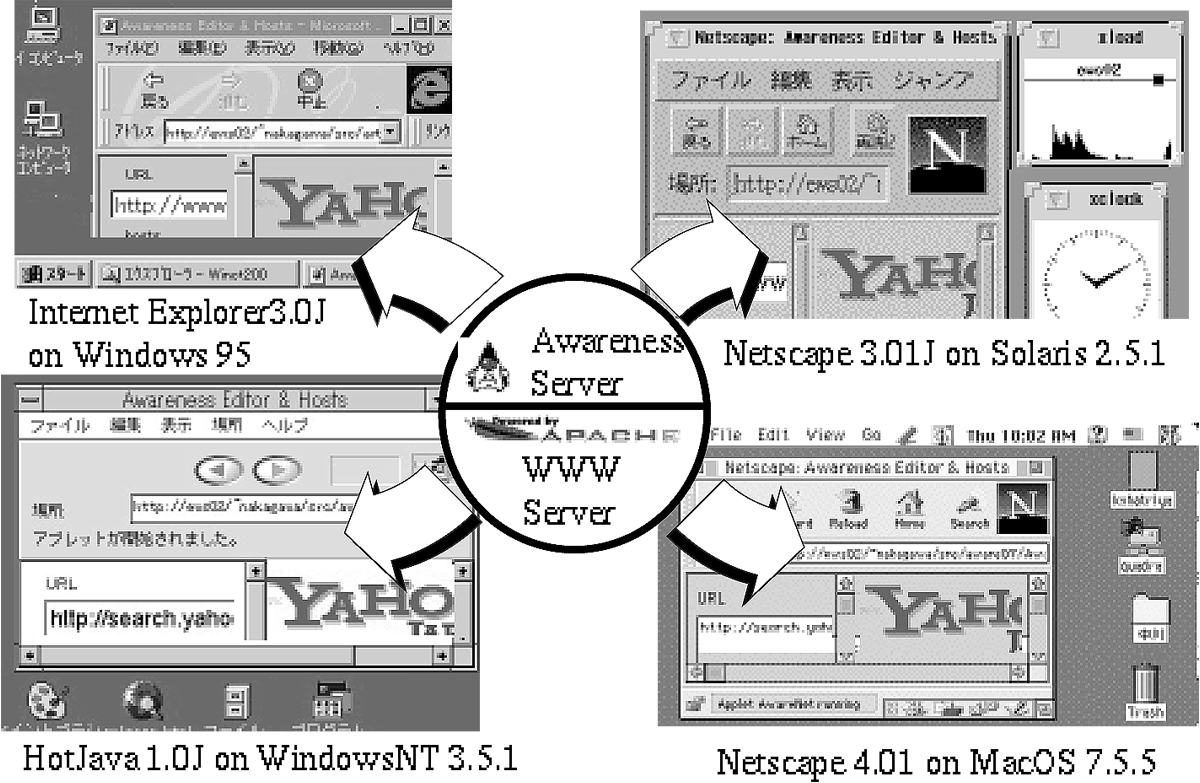
図3.8-4 WWWアウェアネス[中川 98]より引用
双方向通信システムに対面環境とほぼ同等の臨場感を付与する新しい環境を構築するには、視覚と聴覚以外の感覚をも総動員して、その人の持っている気、オーラを伝える必要がある。デジタル情報中心の仮想空間が膨大に膨らみ、従来からある物理空間との距離が隔たりつつある現在、この問題を克服する手段を我々はもっているのであろうか。
デジタル情報の拡大とともに仮想世界と実世界のリアクションに関する研究が進展しつつある。ソニーの暦本[暦本98]、長尾[長尾98]の実世界指向インタフェースの研究で着目している拡張リアリティは、デジタルとフィジカルの融合したユーザインタフェース世界で、ここにおいては情況に基づくアウェアネスを提供しつつ、デジタル情報と身体知が交流し合う世界が構築されつつある。更にMIT の石井の提唱するタンジブルビッツ[石井97, 98]を用いれば、視覚・聴覚のみならず触覚を通してデジタル情報と身体知との交流ができる。ここに、彼のタンジブルメディアのアイデアを拡張すれば触覚、嗅覚、味覚をも利用したその人の雰囲気、感触、気配をも配信できる社会化支援ツール構築の未来を感知しうるのは私だけであろうか。実際に形式知と暗黙知の織りなす未来型双方向通信システムを構築し、仮想世界を通しながら実体験した以上の参画意欲を喚起する社会化支援ツール構築の道のりは遠い。
3.8.4 ナレッジマネジメントに向けて
分節化、連結化、内面化、社会化という知識創造方法論に基づく新しいツール体系の方法論[國藤98a, 98b, 98c]を、知識創造スパイラルを支援する知識創造方法論として提案した。このような研究は最近、ナレッジマネジメントを支援するツールの研究として、世界各国でその萌芽的研究が行われつついる。今後の歴史的必然性を考えると、更に内面化支援ツール、社会化支援ツールの研究開発を行い、それらをナレッジメネジメントの支援技術として集大成する必要がある。
<参考文献>
[電子協92]日本電子工業振興協会編: 人間の思考支援シミュレーションシステム開発に関する調査研究報告書,日本電子工業振興協会,1992.
[藤田97]K. Fujita and S. Kunifuji: A Realization of a Reflection of Personal Information on Distributed Brainstorming Environment, Springer's LNCS 1274, pp.166-181, Mar. 1997.
[富士通研91]富士通研究所国際情報社会科学研究所編: 発想支援システムの構築に向けて,第7回国際研シンポジウム報告書,富士通国際研,1991.
[石田98]T. Ishida(Ed.): Community Computing - Collaboration over Global Information Networks -, John Wiley & Sons, 1998.
[石井94]石井 裕: グループウェアのデザイン,共立出版,1994.
[石井97]H. Ishii and B. Ullmer: Tangible Bits: Towards Seamless Interfaces between People, Bits, and Atoms, Proc. of CHI'97, Atlanta, ACM, pp. 234-241, Mar. 1997.
[石井98]石井 裕: Tagible Bits: 情報の感触/情報の気配,情報処理学,Vol.39 No.8, pp.745-751, 1998.
[Jain98]L. C. Jain and R. K. Jain(Eds.): 2nd International Coference on Knowledge-based Intelligent Electronic Systems, IEEE, Vol.1, pp.359-434, April 1998.
[人工知能96]人工知能学会・計測自動制御学会共催: AIシンポジウム'96: 発想支援システム,機械振興会館,1996年12月4-5日.
[門脇98]門脇千恵: 組織情報の共有過程分析に基づく情報共有促進支援法の研究,北陸先端科学技術大学院大学学位論文,平成10年3月.
[門脇99]門脇千恵,爰川知宏,山上俊彦,杉田恵三, 國藤 進: 情報取得アウェアネスによる組織情報の共有促進支援,人工知能学会論文誌,Vol.14 No.1, Jan. 1999.
[Kakas92]A. C. Kakas, R. A. Kowalski, and F. Toni: Abductive Logic Programming, Journal of Logic and Computation, Vol.2 No.6, pp.719-770, 1992.
[金井97]T. Kanai and S. Kunifuji: Extending Inductive Generalizations with Abduction, IJCAI'97 Workshop on Abduction and Induction, Nagoya Congress Hall, pp.25-30, Aug. 24, 1997.
[加藤97]加藤直孝,中條雅庸,國藤 進: 合意形成プロセスを重視したグループ意思決定支援アシステムの開発,情報処理学会論文誌,Vol.38 No.12, pp.2629-2639, 1997年9月号.
[加藤98]加藤直孝,國藤 進: 異なる評価構造を持つ参加者間の合意形成支援法の提案と実装,情報処理学会論文誌,Vol.39 No.10, 1998年10月号.
[川喜田67]川喜田二郎: 発想法,中公新書,1967.
[川喜田70a]川喜田二郎: 続発想法,中公新書,1970.
[川喜田70b]川喜田二郎,牧島信一: 問題解決学 -KJ法ワークブック,講談社,1970.
[川喜田87]川喜田二郎: KJ法,中央公論社,1987.
[計測自動95a]計測自動制御学会主催: 第17回システム工学研究会「発想支援ツール」,ハイテク交流センター,1995.
[計測自動95b]計測自動制御学会主催: 第18回システム工学研究会「発想支援技術」,鹿児島大学,1995.
[計測自動97]計測自動制御学会主催: 第19回システム工学研究会「発想支援システム」,北陸先端大,1997.
[Kowalski79]R. A. Kowalski: Logic for Problem Solving, Elsevier North Holland, Inc., 1979.
[國藤87]國藤 進: 仮説推論,人工知能学会誌,Vol.2 No.1, pp.22-29, 1987年3月号.
[國藤93]國藤 進: 発想支援システムの研究開発動向とその課題,人工知能学会誌,Vol.8 No.5, pp.16-23, 1993年9月号.
[國藤97]國藤 進: 発想支援グループウェア,ネットワーク及びAI関連新技術に関する調査研究,日本情報処理開発協会先端情報技術研究所,pp.26-30,1997年3月.
[國藤98a]國藤 進: 知識創造プロセスとその支援環境,人工知能学会誌,Vol.13 No.1, pp.26-27, 1998年1月号.
[國藤98b]國藤 進: 「知の大海」へ冒険の旅に,月間アドバタイジング,pp.56-61,1998年6月号.
[國藤98c]國藤 進: 知識創造支援ツール体系,日本創造学会第20回研究大会論文集,北里大学相模原校舎,1998年11月1日.
[國藤研92]國藤研究室主催: 「発想支援ツール」シンポジウム,三菱総研,1992.
[國藤研94]國藤研究室主催: 第2回「発想支援ツール」シンポジウム,富士通幕張シスラボ,1994.
[松浦94]松浦宣彦,岡田謙一,松下 温: 仮想的な出会いを実現したインフォーマルコミュニケーション支援インタフェースの提案,電子情報通信学会論文誌 D-II, Vol.J77-D-II, No. 2, pp.388-396 ,1994.
[宮原98a]M. Miyahara, T. Ino, S. Taniho, and R. Algazi: Important Factors to Convey High Order Sensation, IEICE Trans. CQ, Vol. E81-B, No. 11, Nov. 1998.
[宮原98b]M. Miyahara, K. Kotani, and R. Algazi: Objective Picture Quality Scale(PQS) for Image Coding, IEEE Trans. on Communications, Vol. COM-46, No. 9, Sep. 1998.
[長尾98]長尾 確: モーバイルコンピューティングとエージェント,第12回人工知能学会全国大会チュートリアル講演テキスト,早稲田大学,1998年6月16日.
[中川98]中川健一,國藤 進: アウェアネス支援に基づくリアルタイムなWWW コラボレーション環境の構築,情報処理学会論文誌,Vol.39 No.10, 1998年10月号.
[野口97]野口裕史,國藤 進: データマイニング技術の発想支援ツールへの適用,人工知能学会第29回人工知能基礎論研究会資料SIG-FAI-9701,広島市立大学,pp.36-41,1997年6月6日.
[野中90]野中郁次郎: 知識創造の経営,日本経済新聞社,1990.
[女部田96]女部田武史,國藤 進: 複数のKJ法図解の差異や共通部を可視化する試行支援システムの実現と評価,人工知能学会・計測自動制御学会共催 AIシンポジウム'96 発想支援システム,pp.28-33,1996年12月4日.
[ピアジェ 72]ピアジェ, J: 発生的認識論,文庫クセジュ,白水社,1972.
[ポラニー80]マイケル・ポラニー: 暗黙知の次元−言語から非言語に−,紀伊国屋書店,1980.
[ポパー80]カール・R.ポパー: 推測と反駁,法政大学出版局,1980.
[暦本98]暦本純一: ディジタルとフィジカルの融合: 実世界に展開するユーザインタフェース,第34回人工知能学会基礎論研究会招待講演,SIG-FAI-9802, pp.1-7 ,北陸先端科学技術大学院大学,1998年9月24日.
[サイモン69]H. A. サイモン: システムの科学,ダイヤモンド社,1969.
[サイモン89]H. A. サイモン: 経営行動,ダイヤモンド社,1989.
[高杉96]高杉耕一,國藤 進: ばねモデルを用いたアイデア触発システムの構築について,人工知能学会・計測自動制御学会共催 AIシンポジウム'96 発想支援システム,pp.34-39,1996年12月4日.
[山上93]山上俊彦,関 良明: Knowledge-awareness 指向のノウハウ伝搬支援環境: CATFISH ,情報処理学会93-DPS-59-8, pp.57-64, 1993.
[米盛81]米盛裕二,パースの記号学,勁草書房,1981.