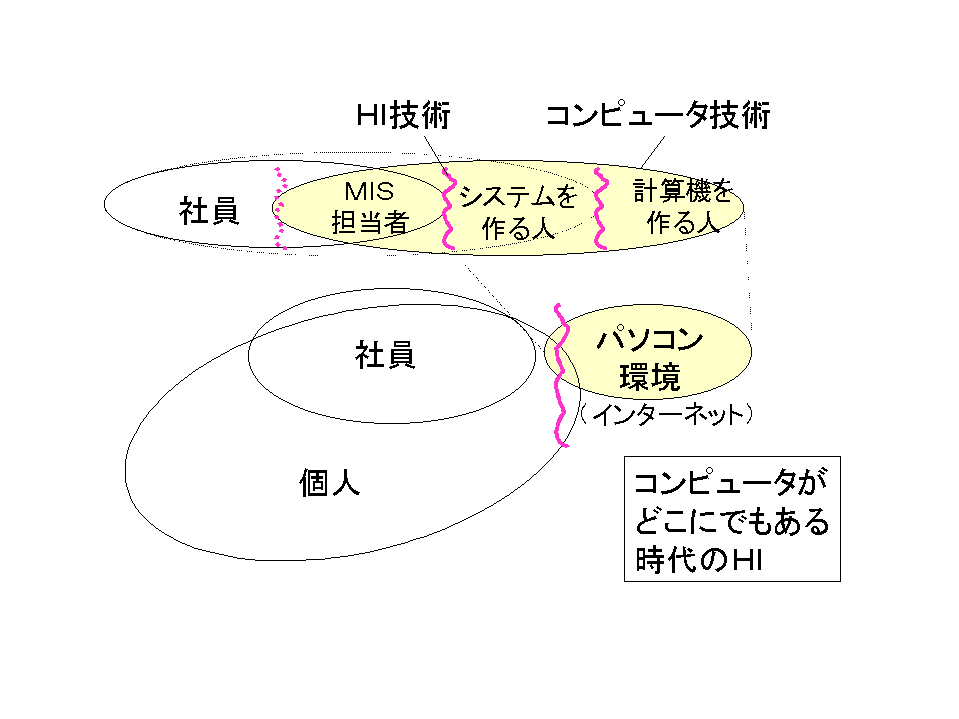
3.4 知的文書インタフェース
3.4.1 コンピュータが見えなくなる日これまでの情報処理化はコンピュータにどう仕事をさせるか?
という専門家を対象としたコンピュータ利用技術を軸として発展してきた。ところがインターネットの普及とパソコンの台頭により、誰もがコンピュータを利用する、あるいは利用せざるを得ない時代に突入しつつある。このようにコンピュータが日用品(
Commodity)となる時代には、その利用インタフェースが非常に重要となる。逆に、誰もがコンピュータの持つ能力を享受するためには、簡単で自然に使えるインタフェースの確立が無ければCommodityとしての普及は難しい。
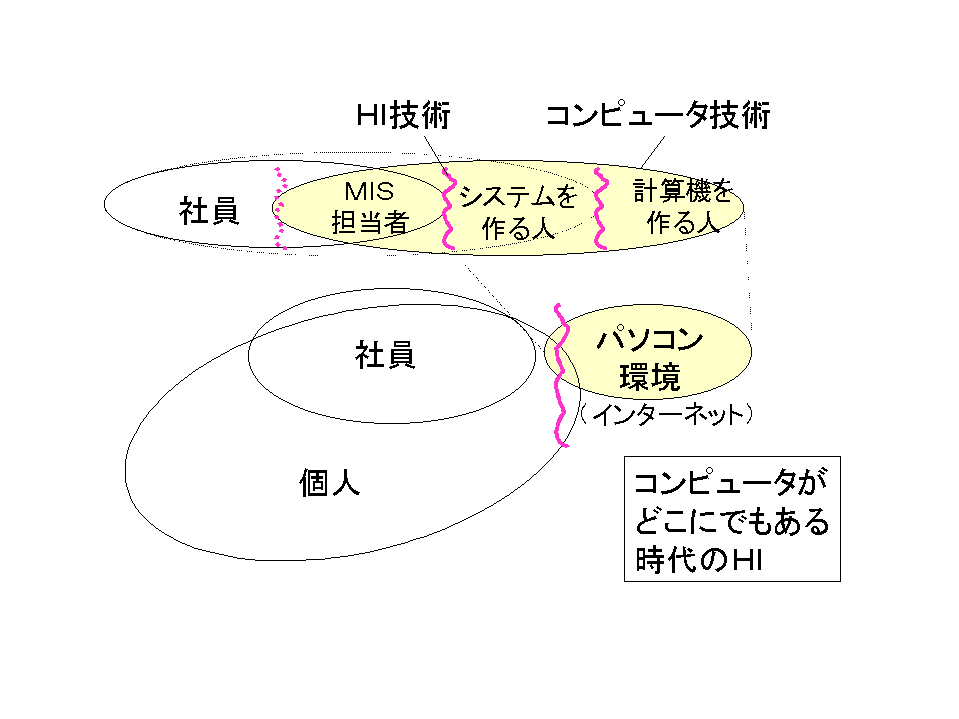
図3.4
-1 コンピュータ利用環境の変化
勿論、これまでもにもコンピュータのヒューマンインタフェースは議論されてきているが、多くの場合は比較的専門家に向けた議論が中心であった。例えばコンピュータの利用者はSE等のシステムを設計しプログラムを開発する人達が主であった。このような状況では、プログラミング言語から始まり、ソフトウェア開発やシステム構築のためのツールやユーザインタフェースが重要であった。またXerox PARCで開発されアップルコンピュータで実用化されたGUI(Graphical User Interface)も、基本的にはファイルやフォルダといったコンピュータ特有の概念を理解していないと使いこなせない。
しかしながら普通の人々がオフィスや家庭でパソコンを利用する際に必要なものはアプリケーションとして提供されている「機能」であって、コンピュータの操作法や動作原理ではない。技術の進歩とはまさにこのようなブラックボックス化に他ならない。車でも電子レンジでも、どれだけ高度な技術が使われていようが、利用者からは「走ること」、「温めること」という要求された機能が実現されればそれで良いのである。技術が未熟なほど面倒な操作が必要なのは歴史の示す通りである。コンピュータは汎用であることが最大の特徴であるが、汎用であるがゆえに操作がわかりにくくなってしまっている。
コンピュータも
21世紀を目前にして、ようやくブラックボックス化される時代になってきたと言える。しかしながらその操作性や外観は旧態依然としており、残念ながら大衆の日用品になるまでに至っていない。本来ブラックボックス化して見えなくなるべきコンピュータが相変わらず自己主張しているのが実状である。これからのコンピュータは本やノート、文房具として我々の身の回りにさり気なく存在すべきである。
3.4.2 なぜ知的文書インタフェースなのか
さて、大衆化したコンピュータは何に使うべきであろうか?
家庭へのパソコン普及率はインターネットブームで上昇したが、やや鈍化傾向にあるようだ。ブームに乗って買っては見たものの、ネットワークへの接続はそれほど簡単ではないし、電話代も高価であるため、埃をかぶっているパソコンも多いと思われる。インターネット以外ではワープロやお絵描きソフト等、単体アプリケーションしかない現状では結局、使い道がないのである。インターネットブームが示唆しているように、大衆化したコンピュータに期待されている機能は結局、人と人とのコミュニケーションであり、情報の共有である。そのための土台となる基本メディアが文書である。実際、
Webの情報も文書であり、電子メールも文書情報である。前者はHTMLによる記述が成功したが、より自由な記述を許すためのXMLに期待が集まっている。SGMLに端を発するこれらのドキュメント記述言語はハイパーテキスト構造を実現するのに適しているがワープロで実現されるような印刷文書には及ばない。一方Adobe社のPDF(Portable Document Format)はもともとデスクトップパブリッシング用に開発されたPostScriptの後継言語であり印刷原稿を記述するのに適しており、Web上で製品カタログ等の印刷品質が必要な情報を表示するのに活用されている。一方、電子メールに関してはテキストベースのプレーンな文書が一般的であるが、手書き情報や図を含むマルチメディア文書の利用が今後期待されている。メール関連ソフトの多くは既にそのような種々のデータ形式を扱うためのインタフェースであるMIMEプロトコルに準拠済みであるが、この機能はまだあまり活用されていない。理由の一端はパソコン側にあり、手書き情報や絵が簡単に扱えないためである。その結果、ちょっとしたメモを送りたい場合にはFAXの方が簡単で早いということになってしまう。
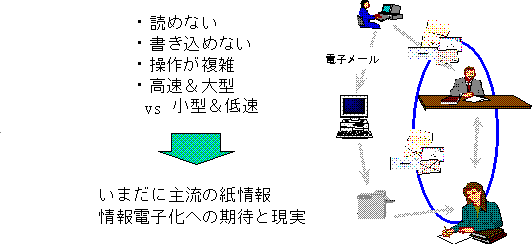
図3.4
-2 パソコンの問題点
このように情報の電子化が進み、ネットワークが日常生活に不可欠のインフラになりつつあるにもかかわらず、現在のパソコンが紙と鉛筆のような手軽さ、簡単さを実現していないため、相変わらず紙ベースの情報処理が主流となっている。電子メールを「印刷して読む」ということもしばしば行われている。これからのコンピュータ利用では手書き情報、絵、写真を含むような文書を簡単に作成でき、且つ、それらをネットワークで自由自在に送れることが必要である。これを総称して知的文書インタフェースを呼ぼう。知的文書インタフェースの実現は、従来の紙ベースの世界とコンピュータによる電子の世界をシームレスに繋ぐことであり、本来の意味での高度情報化社会の実現に他ならない。
3.4.3 知的なインタフェースとは?
人間が行う高度な意味理解、推論等の機能が実現できれば、言いかえればコンピュータが人間と同じ知性を持てば知的なインタフェースの実現は当然可能であるが、そのような根本解決は当分不可能であろう。そこに至る段階として「気の利いたインタフェース」と「自然なインタフェース」の2つが考えられる。前者は人間のやろうとしている操作を理解し次の操作を提案するとか、間違いを自動的に訂正するなどに相当する。商用アプリケーション等でよく採用されているのが「直前の入力を覚えている」方式である。例えばローマ字漢字変換や同じ数字を何度も入力する場合に役に立つ。しかしながら、いつも直前だけを記憶していると提案された候補をキャンセルする操作が煩わしくなる。言語翻訳や音声入力の分野では単語間の繋がりを統計モデルに基づいて予測する更に高度な方式が採用されている。「気の利いたユーザインタフェース」の実現とは、ユーザが何をしようとしているかの意図を抽出することであり、音声認識や画像認識とほぼ同じ問題を解くことになる。例えば、ペン入力で文字の上に×を書いたら「削除」すべきか、そのまま×を書くのか、など書き手には意図が分かっている単純な場合でさえコンピュータ側がうまく認識できない問題が多い。むしろ認識技術をユーザインタフェースの場でもっと高めることが重要である。これはマルチモーダルインタフェースの研究と同じ方向になるが、音声コマンドのような単なる入力手段の多様化ではなく、人間の意図抽出という観点から取り組むべきであろう。
一方、「自然なインタフェース」とは、「人間にとって自然な操作」ということであり、操作のみならずシステムや入力装置の形状、それから受ける印象も含まれる。
D. A. Normanの言うところのVisibilityとMental Modelが重要になる[1]。例えばコンピュータ端末を薄く、紙のようにする[2]というのはメンタルモデルとして紙と鉛筆という非常にわかり易いモデルに持ちこもうとしている。また、ペン入力は「重要な個所をチェックする」という直接動作が自然に行える。(当たり前に普及したマウスであるが、初めて触った人はマウスパッドの端まで移動したあと、どうして良いか戸惑うのが普通である。宙に持ち上げて元に戻すというメンタルモデルを我々は自然には持ち合わせていない)これまでマウスを前提とするユーザインタフェースが主流であったが、チェックする、線を引く等のペン入力操作を多用したユーザインタフェースの追求がもっと研究されるべきであろう。コンピュータの出現により人間の知的作業の増幅が可能になったが、人間の入出力能力はなんら改善されていない。情報洪水の中で自分の考えをタイムリーに整理し発信していくためには、入出力能力の増幅が必須である。例えば昔は否定的であった視線入力がカメラでは実用化されている。人間の何気ない動作からも情報を引き出すセンサ/認識技術の出現が待たれるところである。
3.4.4 研究動向
報告者は紙の持つ利点とコンピュータの持つ能力を融合する端末アーキテクチャを提案しているが[2]、同様の提案はヒューマンインタフェースでは国際的にトップの学会であるCHIでも報告されている[3]。タイプライタ文化の欧米でもペン入力は幾度となくブームとなっており、アルファベット文化=タイプライタではなく、ペンによる自由な書き込みや図の挿入などに潜在的な期待があることが分かる。また、自然なインタフェースとしてカードボックスのパラパラめくりや端末を捻るなどの本を扱うのと同じ操作を実現しようという試みもある[4]。複数のコンピュータ間での情報のやりとりを自然なインタフェースで実現するという
Pick&Drop [5]も注目さている。今後、このようなユーザインタフェースのアイデア提案は活発化すると期待される。
一方、電子ブックの試みも活発化しようとしている。単体での電子ブックは既に製品化されているが、文庫本との比較において「重い、大きい、電池が必要、文字が大きい」等のハンディがあり、必ずしも成功しているとは言い難い。しかしながら新刊本や希少本をネットワークでいつでも入手できるというインターネットの利点を活かした新しい電子ブックコンセプトに新たな期待が高まっている。むしろ、インターネットで電子本を入手可能だが、今のパソコンでは読めない、もっと本を読むような感覚で読みたい、という発想からスタートしている点に注目すべきである。我国では通産省の支援を受けて出版業界と電機メーカとの電子ブックコンソーシアムが昨年10月にスタートした[6]。米国でもいくつかの電子ブック端末が発表されている[7][8]。また、紙のようなディスプレイを目指した新しいデバイス研究が実用化の手前まできている[9]。
3.4.5 今後の研究の進め方
知的文書インタフェースの実現に際しては次の2つの問題がある。
・電子文書フォーマットの統一 ・利用プラットフォームの普及
まず、文書フォーマットであるが、既に世の中にはワープロソフトや表計算ソフトなどが広く流布しており、夫々アプリケーション独自のフォーマットが使われている。インターネットではHTMLやXML等が標準的に使われているが、文書定義をするソースと表示イメージという2種類を扱う不便さがある。PostScript系の文書記述言語も同様に表示プログラムと実際の表示イメージに分離している。いずれの場合も表示イメージを直接保存したい場合にはビットマップ形式で扱う必要がある。またこれらの文書への上書きを実現するにはレイヤ構造の導入が必要となる。ActiveXはこのような異種アプリケーションで作成されたデータを相互に埋め込める枠組みを提供するものであるが、実体はアプリケーション呼び出しメカニズムに過ぎない。理想の姿は、一つの文書データに対して、様々なアプリケーションが働きかけることを可能にすることであろう。例えば、A社のワープロで作成した文書をB社のワープロで読み書きできれば、各自が自分の慣れているワープロで修正・加筆が可能となる。単純なテキストを扱うエディタや電子メールシステムは既にそのような「標準形式+好きなツール」の組み合わせで利用されている。電子文書も同様にユーザの好みを反映できる柔軟性が必要であり、特定ツールを強制するようなことがあってはならない。
第2の問題点として、利用可能なプラットフォームの欠如がある。ヒューマンインタフェース研究の成果はともすれば発想の「面白さ」だけが注目されて、実際に利用されずに終わることが多い。「瞬間芸」という指摘もある。技術情報が溢れている昨今では、似たような発想や夢を語る研究者は多いが、使えるレベルまでまとめる人は少ない。素晴らしいハイテク技術が生まれている一方で、旧態依然とした作業環境がなかなか改善されていないのが実態である。
このような事態が生ずる一つの理由は、量産型の産業構造と厳しい市場競争である。大量生産によってコストダウンしようとすれば自ずからヒット確実な商品に注力するのが当然であって、恩恵を受ける人が少ない物や初期投資がかかるものへの投資意欲がそがれている。それだけ企業の余力が無くなってきたと言える。こういう時期にこそ、国立の研究機関や国の支援が必要である。
例えば、ここで提案しているような紙のような端末などのパーソナル端末は薄くする、あるいは軽くするために高度な実装技術が必要であって、企業の先端技術を必要とするようなプラットフォームをビジネスプランを明確にせずに試作することは許されない。また、ユーザインタフェースに関する評価はある程度の数の利用者で実際に使ってこそ初めて実証できる。国の資金でこのような先端的なユーザ端末をまとまった数開発し、モデル地域のような場所で実験することが有効である(
c.f.フランスのミニテルプロジェクト)。また、電子文書フォーマットに関しても、特定企業の戦略にとらわれず理想形を追求することは問題点を見つけて次のステップに進むために非常に重要である。電子文書をどう実現すべきかは、Web、電子メール、ワープロ等全てのアプリケーションに関わることであり、未来社会のインフラを決定する重要な要因となる。このような研究を国際社会に通じるデファクトスタンダードを生み出せていない日本企業において正当化するのは難しい。米国はインターネットに国策として取り組み、大統領自らが電子メールや
Webを利用して見せたのは記憶に新しい。21世紀に向けてはこれまでの実用化重視路線を反省して、基礎研究に投資する方針を明確に打ち出している。我が国は天然資源が乏しいことから、知的財産を大切に育てることが古くから言われている割に、国・産・学での研究開発がうまく連携しているようには見えない。国への期待は経済状況の厳しい今こそ、将来の糧になる研究を育てることである。そのためには研究テーマの選択もさることながら、技術の流れがどうなるか、今後どのような社会を築くのか、その実現にどのような技術が必要になるか、についての見通し・シナリオ作りが最も重要である。本報告書が少しでも参考になれば幸いである。
<参考文献>
[1] D.A. Norman,
“誰のためのデザイン?(認知科学者のデザイン原論)”、新躍社、1990[2]
横田他、“紙を目指した情報端末”、情処 第56回全国大会、 1B−02、March 1998[3] B.N. Schilit, et. al., “Beyond Paper: Supporting Active Reading with Free Form Digital Ink Annotations”, CHI98, April 1998
[4] B.L. Harrison, et.al., “Squeeze Me, Hold Me, Tilt Me! An Exploration of Manipulative User Interfaces”, CHI98, April 1998
[5] J. Rekimoto, “A Multiple Device Approach for Supporting Whiteboard-based Interactions”, CHI98, April 1998
[6]
歌田、“電子書籍実験本の未来をひらくか”、季刊 本とコンピュータ、No.6、1998[7] http://www.rocket-ebook.com
[8] http://www.everybk.com
[9] P. Drzaic, et.al., “A Printed and Rollable Bistable Electronic Display”, SID 98 Digest, 1998