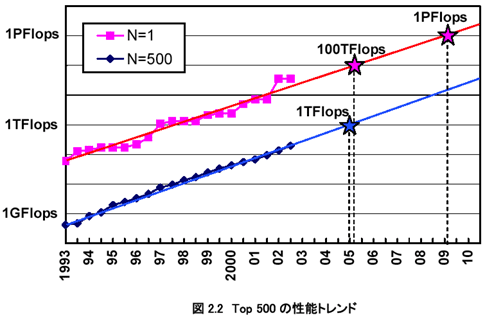|

第2章 米国のハイエンドコンピューティング研究開発動向

今回のテーマは”From Terabytes to Insights”(テラバイトから洞察へ)であり、ハイエンドのコンピューティング能力がもたらす科学研究の飛躍的進歩といったところに主眼が置かれていたようである。基調講演や招待講演でも科学研究に対するハイエンドコンピューティングの貢献の大きさと、さらなる高性能化への期待が述べられていた。
SC2002の主要な話題は、やはり地球シミュレータをはじめとするハイエンドプラットフォームとグリッドおよび高速ネットワーク関連であった。展示関係ではCRAY X1、IBM p655、Origin 3900などのサーバ新製品の展示と科学技術アプリケーションのデモによる高性能のアピールが目立った。
なお、SC2002での講演、発表および展示内容については、東京大学の小柳教授のレポートが詳しいので、そちらを参照されたい。
(http://olab.is.s.u-tokyo.ac.jp/~oyanagi/reports/SC2002)
次回(第16回)SC2003は、アリゾナ州フェニックスで開催される予定である。
|

参照サイトはhttp://www.sc-conference.org/sc2003/
テーマは”Igniting Innovation”(革新に火をつけよう)である。
(1)地球シミュレータの与えたインパクト
SC2002における最大の話題は、2002年6月にその圧倒的な性能によりTop 500リストの第1位に躍り出た地球シミュレータであった。会期中には地球シミュレータセンター長の佐藤哲也氏の招待講演があったほか、米国政府のNSFやDOEのディレクターの講演でもしばしば言及されていた。また、投稿された論文の中から選ばれて、Gordon Bell Awardsを受賞した5件の論文うちの3件が地球シミュレータ関連であった。さらに、パネルディスカッションではそのものずばりの”The 40Tflop/s Earth Simulator System: Its Impact on the Future Development of Supercomputing”というタイトルのセッションまで設けられ、活発な議論が行われるなど、その影響の大きさがうかがえた。
上記のように地球シミュレータが大きく取り上げられた背景には、「危機感を煽って米国政府からのR&D予算獲得の口実とする」という理由も存在したであろうが、以下のような議論を呼び起こすきっかけを作ったということもあったと思われる。
① 実効性能に関する議論
現在の主流は、汎用スカラープロセッサと汎用ネットワーク、すなわちCommodity Off-The-Shelf(COTS)製品を使用した超並列スカラー型システム(PCクラスタを含む)である。しかしこの方式における実効性能(実アプリケーション全体を通しての平均Flops)は、一般的にピーク性能の10パーセント程度と言われており、ベクトル型システムより劣っている。米国が捨てたベクトル方式を採用した地球シミュレータが、実アプリケーションの「全球大気大循環シミュレーション」でピーク性能の66パーセント(26.58TFlops)という驚異的な実効性能を実現したことが、システムアーキテクチャと実効性能についての議論をあらためて呼び起こしているように見える。② ハイエンド領域もCOTSでいいのか?
米国のハイエンドコンピュータの主流は、上記のCOTS製品を使用したものである。安価な点において、この方式の一般市場での優位は、もはや動かしがたいところまで来ている。しかし、国家の安全保障や科学研究などの最高性能を必要とする領域で、COTSをベースとしたシステムしか解がないことへの問題意識も高まりつつある。地球シミュレータは、わが国ではさほど話題になっていないが、それとは対照的に、米国の関係者には非常に大きなショックを与えたようである。科学技術における米国のリーダーシップの危機といった論調まであり、DOEなどが中心となって2年以内に地球シミュレータの性能を凌駕するシステムを開発しようと躍起になっている。
一方、わが国は地球シミュレータ以後、国が主導する高性能プラットフォーム開発の具体的計画を持っていない。このままだと2~3年後には米国が再び世界一の座を取り戻し、ハイエンドコンピューティング分野における日本発のセンセーションも、一時的な現象に終わるのではなかろうか。
(2)Top 500にみる性能動向
毎年6月にドイツで開催されるISC(International Supercomputer Conference)と11月に開催されるSCにおいて、”Top 500 Supercomputer Sites”(LINPACKベンチマークによる性能測定結果の上位500サイト)が発表されている。
SC2002で発表されたTop 500には、地球シミュレータに続き、新たに2位と3位にロスアラモス国立研究所(LANL)のASCI Qがランクされた。また、5位にローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)のNetworX社製PCクラスタ(Xeon 2.4GHz x 2,304プロセッサ)、8位にNOAAのHPTi/Aspen Systems社製PCクラスタ(Xeon 2.2GHz x 1,536プロセッサ)と2台のシステムがPCクラスタとしては初めてTop 10内にランクインするなど、全般的にPCクラスタの増加が目立っている(付表1、2参照)。
図2.2は1993年から2002年まで10年間のTop 500の1位と500位の性能推移をグラフにしたものである。過去10年間は年率1.9~2.0倍の割合で性能が向上しており、今後もこの傾向が続くとすれば、2005年に1位が100TFlops、500位が1TFlopsに達し、さらに2009年には1位が1PFlops(ペタフロップス)に達すると予想される(あくまでもLINPACKベンチマークの性能であり、理論ピーク性能ではないことに注意)。